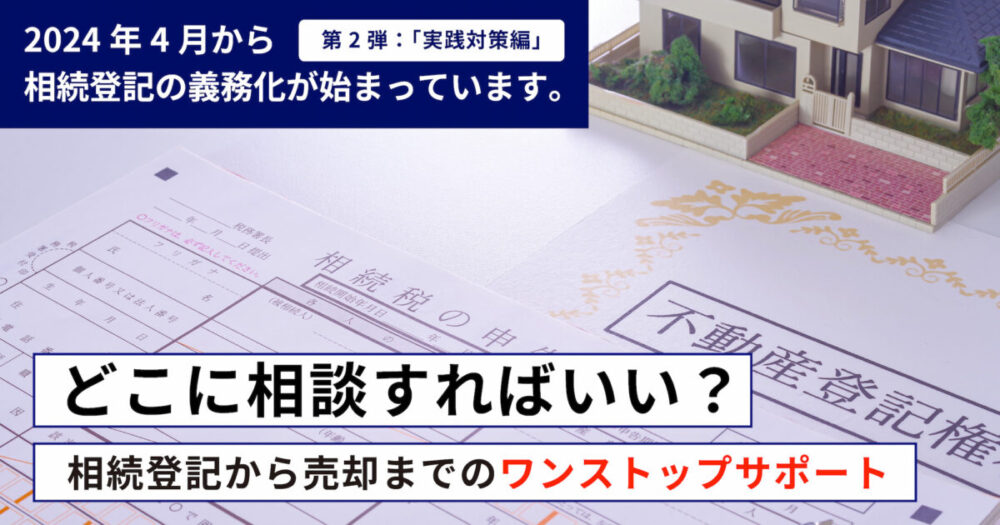令和6年4月から相続登記の義務化が始まっています。
第2弾:「実践対策編」
もうすぐお盆。実家の相続登記、お済みですか?
2025年も半分が過ぎ、もうすぐお盆の季節がやってきます。久しぶりに家族が集まる機会に、
「そういえば、おじいちゃんの家の名義変更ってどうなってる?」
「相続登記って義務化されたんだよね?」
そんな話題が出るご家庭も多いのではないでしょうか。
前回のブログ「基礎知識編」でもお伝えしましたが、相続登記義務化から1年以上が経過しています。
そして、法務省によれば相続登記の申請件数は前年比約1.5倍に急増しているとのことです。
でも、
「そう言われても、どこに相談すればいいの?」
「手続きって複雑そう…」
と悩んでいる方も多いはず。
今回は、土岐市・多治見市・春日井市・名古屋市を中心に、相続登記から不動産売却まで、具体的にどう進めればいいのかをご説明します。
もちろん、他の地域にお住まいの方にも役立つ手続きの流れや費用の目安など、共通する大切な情報もたくさんありますので、ぜひ最後までお読みください。
公的機関に相談?それとも民間のサポート?
公的機関での相談、実はこんな現実が…

例えば土岐市なら毎月第3火曜日、多治見市なら毎月4回の法律相談があります。でも、実際に利用された方からはこんな声が…
- 「相談時間が20分だけで、詳しく聞けなかった」
- 「予約が取れるまで1ヶ月待った」
- 「結局、自分で司法書士を探すことになった」
公的機関では基本的な相談はできますが、実際の手続きは自分で進めるか、別途専門家を探す必要があります。
地域によって全く違う、相続不動産の課題
土岐市・多治見市のような郊外エリアと、春日井市・名古屋市のような都市エリアでは、相続不動産の課題が大きく異なります。
郊外エリアでは:
- 空き家率が高く(土岐市13.6%、多治見市10.9%)、管理が大変
- 農地相続は10ヶ月以内の届出が必要(違反すると10万円以下の過料)
- 中山間地域の不動産は買い手が見つかりにくい
都市エリアでは:
- マンション相続で管理費・修繕積立金の滞納を引き継ぐリスク
- 高蔵寺ニュータウンなど築40年以上の物件の処分が困難
- 名古屋市内は司法書士報酬も高め(12万円~20万円)
【参照】
– 国土交通省 https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/akiya_portal/gifu.html
-ダイヤモンド不動産研究所 https://diamond-fudosan.jp/articles/-/1112679
-春日井市「春日井市空き家等対策計画」
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/817/R021021_shiryou01.pdf
– 名古屋市 「令和5年 住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地)住宅及び世帯に関する基本集計
https://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000181065.html
なぜワンストップサポートが必要なのか
相続登記から売却まで、通常はこんなに多くの専門家が必要です:
- 司法書士:相続登記手続き(費用:8万円~15万円)
- 不動産会社:査定・売却活動
- 解体業者:古い建物の解体(必要な場合)
- 税理士:相続税・譲渡所得税の相談(必要な場合)
それぞれ別々に依頼すると、情報伝達ミスや手続き漏れのリスクがあります。「相続登記は終わったけど、その後どうすればいいかわからない」という方も多いのが現実です。
実は、法務省の調査によると、相続登記義務化を知っていても「どこに相談したらよいのかわからない」という方が最も多いんです。
つまり、
「何から始めればいいの?」
「誰に相談すればいいの?」
と悩んでいるのは、あなただけではありません。
むしろ、ほとんどの方が同じような不安を抱えています。
相続の手続きは人生で何度も経験するものではありませんから、わからないことだらけで当然です。
「こんな初歩的なことを聞いてもいいのかな…」
なんて心配する必要は全くありません。
みなさん最初は同じスタートラインに立っています。
-参照 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
林組なら、そんな空き家・相続に関するお悩みを持った方を、ワンストップで初回相談、司法書士との連携から売却後のサポートまで一貫して解決いたします。
お気軽にご相談ください。
林組のワンストップサポートで、相続の悩みを一気に解決
林組の「顔の見える経営」でもお伝えしたように、私たちは地域に根ざした総合不動産サービスを提供しています。
林組なら、こんなにスムーズ:
STEP1:無料相談でまず現状把握
- お電話一本で相談予約
- じっくり時間をかけてお話を伺います
- 必要書類や手続きの流れをわかりやすく説明
STEP2:提携司法書士をご紹介
- 信頼できる司法書士との連携
- 面倒な書類収集もサポート
- 費用も明確にご提示
STEP3:相続登記後の最適な活用提案
- 売却査定(無料)
- 賃貸活用の可能性検討
- 解体・リフォームのご提案
STEP4:売却まで一貫サポート
- 地域特性を活かした販売戦略
- 必要に応じて解体工事も自社対応
- 売却完了まで責任を持ってサポート
東濃地域の農地相続や、都市部のマンション相続など、地域ごとに異なる課題にも対応いたします。
今すぐ相談すべき3つの理由
1. 義務化の期限は刻々と迫っています
相続から3年以内の登記が義務。
過去の相続も2027年3月31日までに登記が必要です。
まだ過料の適用事例はありませんが、専門家によると意図的に長期間放置された場合は、今後過料が適用される可能性があります。

2. 放置すればするほど手続きが複雑に
時間が経つほど相続人が増えたり、必要書類の取得が困難になったりします。
さらに深刻な問題が進行中です。
現在、日本全国で「誰の土地かわからない」不動産が日本の国土面積のおよそ22%、なんと九州全体に匹敵する面積にまで拡大し、大きな社会問題となっています。
原因は、相続登記をしないまま放置されたり、相続した方が引っ越しても住所変更手続きをしなかったりすることで、所有者の行方がわからなくなってしまうことです。
この結果、道路建設や災害復旧工事ができない、空き家問題が解決できない、土地売買に支障が出るなど、様々な問題が発生しています。
そこで国は、この問題を解決するため段階的に制度を厳格化:
- 2024年4月〜:相続登記義務化(3年以内、違反時10万円以下の過料)
- 2026年4月〜:住所変更登記義務化(2年以内、違反時5万円以下の過料)
つまり、相続不動産をお持ちの方は「相続登記」だけでなく、その後引っ越しをした場合の「住所変更登記」も忘れずに行う必要があります。
これは単なる義務の追加ではなく、社会全体で土地の所有者を明確にし、有効活用できる環境を整えるための重要な取り組みなのです。
放置すればするほど手続きは複雑化し、将来的にはより厳しいペナルティが科される可能性もあります。早めの対応が、ご自身にとっても社会にとってもベストな選択です。
-参照 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
3. 早期対応で税制優遇も活用可能
手続きが複雑になる前に対応すれば、大きな節税メリットも。
相続した空き家を売却する場合、最大3,000万円の特別控除が受けられますが、これには「相続開始から3年以内の売却」という期限があります。この特例を活用すれば、売却益にかかる税金を大幅に軽減できる可能性があります。
また、相続登記の登録免許税についても、条件を満たせば免税措置が適用される場合があります。
つまり、早期対応は:
- 手続きの簡素化
- 税制優遇の活用
- 将来的なペナルティ回避
という「三重のメリット」があるのです。
逆に、時間が経ってしまうと、これらの優遇措置を受けられなくなってしまいます。お悩みの段階でも構いませんので、まずは現状を整理し、最適なタイミングと方法をご相談ください。
まずは無料相談から始めませんか?
お盆で家族が集まるこの機会に、相続について話し合ってみませんか?
「相続登記って何から始めればいいの?」
「実家を相続したけど、住む予定がない」
「農地の相続で困っている」
など、どんなお悩みでも結構です。
土岐市から名古屋市まで、東濃地域・愛知県の相続不動産のことなら、林組にお任せください。
相続登記から売却まで、ワンストップでサポートいたします。
\ 相続登記について、お気軽にご相談ください /
TEL:0572-56-6950
営業時間 10:00~19:00
相続不動産の売却をお考えの方は、併せて林組の不動産売却サービスもご覧ください。
林組では地域に根ざした確かな実績で、お客様の大切な資産を最適な形で次世代へつなぐお手伝いをさせていただきます。
相続登記の義務化は、決して他人事ではありません。
今すぐ確認し、適切な対応を取ることが、将来の安心につながります。
まずはお気軽にご相談ください。
私たち林組が、皆様の笑顔のために全力でサポートいたします。
相続 ・ 空き家に関する不動産売却や登記義務に関して、法的なこと、手続きの流れなど、下記よりご確認いただけます。

次回のブログでは、
「相続した実家をどう活用するか?」
について、具体的な活用法と税制優遇について詳しくご紹介します。
併せてお読みください!
\ お住まいのこと、お気軽にご相談ください /
TEL:0572-56-6950
営業時間 10:00~19:00
施工事例や地域の情報、住まいづくりのコツなどを発信しています。
皆様の「いいね!」や「フォロー」が私たちの励みになります